一

p.27 “だがもしかすると、最初のひと筆がまだおろされていないのかもしれない。”
p.27 “たぶん彼は、描きかけの画布の表面が後方に投げかける、いわば潜在的なあの大きな籠のなかから出てきたところで…”

pp.27-28 “あたかも画家は、自分が表象されている絵のなかに見られると同時に、自分が熱心に何かを表象している絵を見ることはできないとでもいうように。彼は、両立しがたいこの二つの可視性の境界に君臨しているのである。”
p.28 “目に見えぬ一点を凝視しているのだ。”
p.28 “その一点こそ、われわれ自身、われわれの身体であり、われわれの顔であり、われわれの眼であるからだ。”
p.28 “…だから二重の意味で目に見えないのである。”
p.28 “…見つめているときわれわれの視線がわれわれ自身に隠されてしまう…”
p.28 “画家の眼からその見つめているものまで、見つめているかぎりわれわれの見おとすことのできぬ、断乎たる一本の線が走っている。”
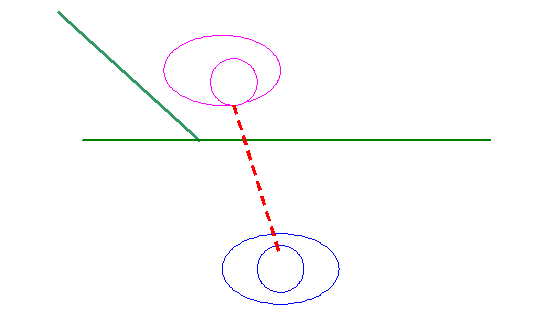
p.28 “この点線こそ、確実にわれわれのもとに達し、われわれを絵の表象と結びつけてくれるものにほかならない。”
p.28 “…純粋な相互性…”
p.28 “…可視性をあらわすこの細い線は、不確かさと交換と身のかわしの入りくんだ、ひとつの網目全体を含んでいる。”
p.28 “…われわれは画家によって追い払われ…(中略)…モデルそのものによって置きかえられてしまう。”
pp.28-29 “…押しかけてくる鑑賞者とおなじ数のモデルを受けいれるわけだ。”
p.29 “…見るものと見られるものとがたえずたがいに入れかわる。”
p.29 “…主体と客体、鑑賞者とモデルとは永遠にその役割を換えつづけていく。”
p.29 “…大きな画布は、第二の機能をはたすこととなる。”
p.29 “…自分がだれか、自分が何をしているのかわれわれは知らない…”
p.29 “しかし彼の眼の注意ぶかい不動性はべつの方向のことを思わせずにはおかない。”
p.29 “…この絵の絵を規定する潜在的な三角形 を律するのである。つまり、その頂点―可視的な唯一の点に画家の眼、底辺の一方にモデルのいる不可視の場所、他方に、裏がえしにされた画布のうえにきっと素描されているにちがいない形象がある、そのような三角形をだ。”
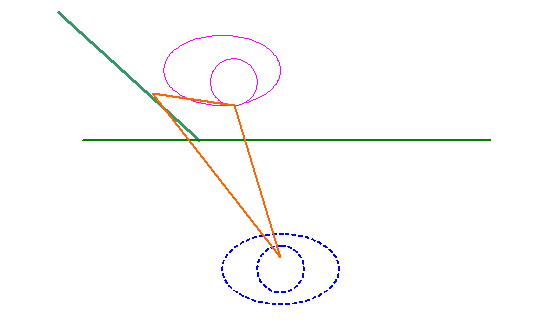
p.29 “…画家の眼は鑑賞者をとらえてむりに絵のなかへ連れこみ、…(中略)…輝く可視的な形相を彼から先どりし、それを裏がえしにされた画布の近づきえぬ表面に投射するのである。”
p.29 “…みずからの不可視性を見る…”
p.30 “(部屋と画布、すなわち、画布のうえに表象された部屋と画布のおかれている部屋のことを言いたいのだが)”

p.30 “…作者は一組の絵を表象している。そして壁にかかったこれらの油絵のうち、一枚だけが特異な光で輝いているのだ。”

p.31 “だがこれは絵ではない。鏡である。”
p.31 “けれどもだれもそれを見つめてはいない。”
p.31 “たしかにそれは可視的なものにほかなるまい。だがどの視線も、それをとらえ、顕在的なものとして、とつぜん熟したその光景の果実を享受しようとはしないのである。”
p.31 “このような無関心に匹敵するものとしては、鏡のそれがあるばかりだと認めなければなるまい。”


p.31 “オランダ絵画では、鏡が二重化の役割をはたすという伝統がある。”
p.31 “だがここでは、鏡はすでに語られたことについては何も語ってはいない。”
p.32 “…鏡は、絵そのものとおなじパースペクティヴを示す線によってつらぬかれているのにちがいない。”
p.32 “…そこで捕捉しうるものをも無視して表象の場全体をよこぎり、あらゆる視線の外にあるものにたいして可視性を回復させてやるのだ。”
p.32 “鏡のなかに映しだされているもの、それこそ、画面のあらゆる人物が視線をまっすぐに伸ばし凝視しているものにほかならない。”
p.32 “これら二種類の形象は、どちらもおなじように近よりがたいものではあるが、それはそれぞれ別の理由にもとづく。つまり、前者では、この絵に固有のものであるコンポジションの結果により、後者では、一般にあらゆる絵の実在そのものを司る法則による。”
p.32 “鏡こそ、絵のなかに表象された空間とその表象としての本性とを同時にゆさぶる、可視性の換位を保証するものにほかならぬ。”