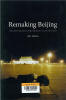|
|
 |
関根伸夫『風景の指輪』(図書新聞、2006年)
<H19年度科研> |
|
|
 |
中川久定ほか編『十八世紀における他者のイメージ―アジアの側から、そしてヨーロッパの側から』(
河合文化教育研究所、2006年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
中沢新一『芸術人類学』(みすず書房、2006年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
ジャック・アダ『経済のグローバル化とは何か』(ナカニシヤ出版、2006年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
塩原良和『ネオ・リベラリズムの時代の多文化主義―オーストラリアン・マルチカルチュラリズムの変容』(三元社、2005年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
島本浣『美術カタログ論―記録・記憶・言説』(三元社、2005年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
藤川隆男編『白人とは何か?―ホワイトネス・スタディーズ入門』(刀水書房、2005年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
ウルリッヒ・ベック『グローバル化の社会学』(国文社、2005年)
<H17年度科研> |
|
|
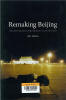 |
ウー・フン『北京再建』(シカゴ大学出版、2005年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
ヨハンナ・ドゥルッカー『甘美な夢―現代美術と共謀』(シカゴ大学出版、2005年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
セルジュ・フォシュロー『20世紀の人類と美学運動』第1巻(2005年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
タシタ・ディーン+ジェレミー・ミラー『場所』(テムズ&ハドソン、2005年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
ジェーン・ロバートソン+クレイグ・マクダニエル『現代美術の主題―1980年以後の視覚芸術』(
プリンストン大学出版、2005年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
ブルース・アルトシュラー編『新しきものの蒐集―美術館と現代美術』(
プリンストン大学出版、2005年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
トマス・ダコスタ・カウフマン『美術地理学に向けて』(シカゴ大学出版、2004年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
絓秀実『革命的な、あまりに革命的な―「1968年の革命」史論』(作品社、2003年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
『アルファベットから引く外国人名よみ方字典』(日外アソシエーツ、2003年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
ロイ・ハリス『美術語りの必要性―西洋の伝統における美術を語る言葉』(コンティヌアム、2003年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
ロバート・S・ネルソンほか編『美術史を語る言葉』(第2版)(シカゴ大学出版、2003年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
トマス・ブートー編『ハンス・ウルリッヒ・オブリスト―インタヴュー』第1巻(2003年)
<H15年度校費> |
|
|
 |
ケン・エーリッヒ+ブランドン・ラベル編『界面張力―場所をめぐる問題群』(2003年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
ミウォン・クウォン『場所から場所へ―場所性の美術とアイデンティティ』(2002年) ※ペーパーバック版=2004年
<H17年度科研> |
|
|
 |
ユ・シャオ=ウェイ編『中間領域をめぐって―ホウ・ハンルウ』(2002年)
On The Mid-Ground
<H15年度校費> |
|
|
 |
ニコラ・ブリオー『関係性の美学』(英語版)(2002年)
※「光州ビエンナーレ2004」展図録論文で参照される。
<H16年度校費> |
|
|
 |
キャロル・L・ブレッケンリッジほか編『世界市民主義』(デューク大学出版、2002年)
<H19年度校費> |
|
|
 |
ヴェルナー・シュマーレンバッハ『芸術!―語り、論争、記述』(2000年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
モーリス・ロシェ『巨大イベントと近代性―地球文化の興隆におけるオリンピックと万博』(2000年)
<H16年度校費> |
|
|
 |
ニコラス・トーマス『所有―民族芸術/植民地文化』(テムズ&ハドソン、1999年)
<H16年度校費> |
|
|
 |
フレドリック・ジェイムソンほか編『地球規模化の文化』(デューク大学出版、1998年)
<H17年度科研> |
|
|
 |
ハロルド・マクスウェイン・ジュニア『関係性の美学』(1994年)
※「光州ビエンナーレ2004」展図録論文で参照される。
<H16年度校費> |
|
|
 |
セルジュ・ギルボー『いかにしてニューヨークは近代美術の観念を盗んだか―抽象表現主義、自由、冷戦』
(英語版)(1993年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
『世界博覧会―アメリカ国際博覧会における帝国の展望1876-1916』(
シカゴ大学出版、1984年)
Robert W. Rydell, All the World's a Fair: Visons of Empire
at American International Expositions, 1876-1916 (Chicago: U of Chicago
P, 1984)
<H16年度校費> |
|
|
 |
ハラルド・ゼーマン『オブセッション美術館』(1981年)
<H18年度科研> |
|
|
 |
ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラトー』(1980年)
<H18年度科研> |
|
|
|
|