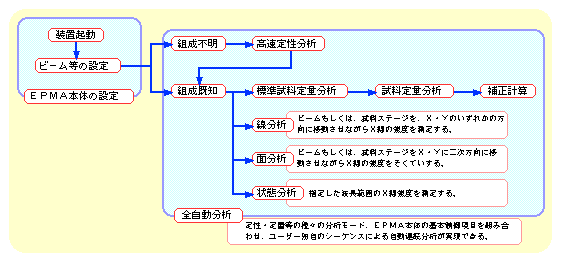1.装置の概要
機種 株式会社島津製作所製 EPMA−V6,
定格出力 30 kV,250μA.
EPMA−V6は,他のEPMAと異なり,特に微量分析,状態分析に優れた性能を持っているため,様々な物質について従来行っていた成分分析(定性・定量)だけにこだわらない多角的なキャラクタリゼーションが行える装置です.
2.装置の原理
試料に細く絞った電子線を照射し,そこから発生する特性X線を波長分散分光器で分離検出して,微小部の元素分析を行う.また,走査型電子顕微鏡と同じように,細く絞った電子線を試料上に走査し,発生する二次電子を利用して試料の観察を行うこともできる.
3.試料および得られる情報
試料に細く絞った電子線を照射すると,そのエネルギーの大部分は熱に変換されますが,他は図1に示すように多くの信号を発生させます.これらの信号を適切に利用する事によって,微小部の
1)表面分析
2)元素分布
3)結合状態分析
4)内部特性・結晶構造の解明
を行うことができます.試料は固体であればほとんど全ての分析が可能で,4Be 〜 92U の全ての元素の検出が可能です.以下はそれぞれの信号について簡単に紹介します.
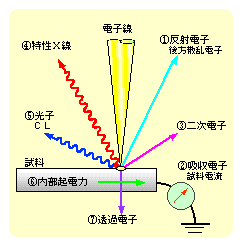 €反射電子(BSE)
€反射電子(BSE)試料表面の凹凸の様子を調べたり,組成の違いを推定するのに用いられます.
吸収電子(SC)
試料電流とも呼び,主として入射電子密度のモニターとして用いられます.
¡二次電子(SE)
およそ6nm の分解能が得られますので,数万倍の拡大像の観察が可能です.二次電子像は焦点深度が深いので凹凸の激しい複雑な形状のものでも観察できるのも特徴の一つです.
¤特性X線
分析に利用される最も重要な信号で,特性X線と原子番号の間には一定の関係( Moseley )があり,この波長を調べることで元素の定性分析が,さらにその強度を測定することによって定量分析を行うことができます.
特性X線を検出する分光器には,X線が波の性質を持つことを利用して分離する波長分散型分光器( WDS ),X線がエネルギー粒子の性質を持つことを利用して分離するエネルギー分散分光器( EDS )があります.
¦光子(カソードルミネッセンス)
X線に比べより長い波長の光(近紫外,可視,近赤外)であるカソードルミネッセンス( CL )は,成分や結晶状態特有のスペクトルを持ち,状態変化,内部特性を知るために用いられます.
©内部起電力及びª透過電子
半導体のP/N結合部等では電子線照射により内部起電力が生じたり,試料が薄い場合,入射電子は試料を突き抜け,透過電子として検出し,組織の様子を観察できます.
4.測定方法
測定は,附属のワークステーションで制御し,図2のフローチャートにしたがって,各分析の編集等を行い,高速定性,定量分析,面分析等を行います.また,これらの分析は,全自動分析により分析位置,分析内容,本体の設定等を自動に行うことができます.