トロント大学胸部外科留学からの帰朝報告 – 村上 順一
はじめに
2017年9月1日よりカナダ国オンタリオ州トロントにあります、University Health Network、Toronto General Hospital、Latner Thoracic Surgery Laboratories、Marc de Perrot Lab.にPostdoctoral fellowとして2年間留学をしました。簡単ではありますが、留学に至った経緯、留学内容について報告します。
留学に至った経緯
私は自治医科大学を2004年3月に卒業し、卒後9年間、義務年限を務めました。学生時代はへき地医療を実践できるような総合診療医を目指していましたが、山口県立中央病院(現山口県立総合医療センター)での研修の中で、外科医を目指すようになりました。当時、同院長を務めていらっしゃいました江里健輔前教授に濱野公一教授をご紹介いただき、卒後3年目(2006年)に羊翔会に入会、社会人大学院に入学させていただきました。
2008年に応用医工学修士課程、2010年に同博士課程を無事に卒業できました。外科医を志す前から海外留学を夢みていましたが、この大学院時代に濱野教授、上田和弘先生(現鹿児島大学所属)、李先生(現長崎大学所属)から指導を賜る中で、基礎実験と臨床とが連動した研究にやり甲斐を見出し、トランスレーショナル・リサーチ先進諸国への留学を意識しはじめました。2013年に義務年限が明け、第1外科に入局しました。1年間の各班ローテーション後に、呼吸器班に所属させていただきました。入局当時は外科専門医も取得しておらず、ましてや呼吸器外科専門医はまだまだ先、、、と自分の中で焦燥感が高まっていたのを覚えています。
上田先生、田中俊樹先生、林雅太郎先生をはじめ医局員や同門会員皆様のおかげで、2014年に外科専門医、2016年に呼吸器外科専門医を取得することができました。2016年初旬から濱野教授、上田先生、田中先生には海外留学の相談をしていましたが、2017年1月に田中先生を通じて海外留学の具体的な話が進んでいきました。本当に突然、その日はやってきました。留学先からcurriculum vitae (CV)の提出を求められ、数時間でcover letter、CVを完成させ、田中先生にチェックいただき、急いでメールを返信しました。メール送信後、数時間でOkay with my pleasure, I am looking forward to working with you.と返信が来たのを今でも鮮明に覚えています。その後、海外留学の手続きを進め、2017年8月下旬にカナダ、トロントに向けて出発しました。
留学環境

トロントはオンタリオ州最大の都市かつ州都であり、カナダ国最大の都市であります。オンタリオ湖岸の北西に位置し、人口はおよそ260万人です。北米有数の世界都市であり、2010年の都市圏人口は北米ではニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴに次ぐ4番目の大都市です(Wikipediaより引用)。気候は北海道に近く、冬は雪が少ないですが、-20から-30℃まで下がることもあり、都心部特有の強いビル風により体感温度はさらに低くなります。
トロントは「移民の街」のため、街中を歩くと英語はもちろん、それ以外の言語も聞こえてきます。文化的背景が異なる人々と日常的に接するためか、まずはお互い親切であることが基本マナーのようです。トロントについた当初は何度となく、現地の方に助けられました。また全く見ず知らずの人も道端で声をかけてくれます。「今日は天気がいいね」「どこから来たの?」「その服どこで売ってんの?」「このコーヒー美味しいよ。飲んでみる?」「オススメのレストラン知らない?」など、人との距離はとても近いです。また様々な国からの移民が多い故、様々な訛のある英語(もちろん自分を含む)を体験することができました。
個人的な感想としては南米の英語が聞き取りづらく、はじめはコーヒー1杯さえも注文できませんでした。


トロント大学の歴史としては、1921年にインスリンが発見され、その功績を称えてカナダドル紙幣にインスリンの薬瓶が描かれています。また1984年にはTリンパ細胞受容体が世界で初めてクローニングされ、免疫療法の根幹を支えています。その附属病院であるToronto General HospitalはUniversity Health Network(UHN)に属し、 Princess Margaret Cancer Hospital、Toronto Western Hospital、Toronto Rehabilitation Institute などと共に医療集合体を形成しています。私は Toronto General Hospitalの胸部外科が運営するLatner Thoracic Surgery Laboratoriesの Marc de Perrotラボに所属しました。 Latner Thoracic Surgery Laboratoriesは主に呼吸器外科医が主催する7つのラボで構成されています。ラボを運営しているのは研究資金を獲得しているstaff surgeon 以上です。Staff surgeon の下っ端は私と同年代でしたが、外科医としての給料は5,000万円から7,000万円くらいで、研究費は年間2,000万から3,000万くらいあると聞きました。同病院は1983年に世界初の臨床肺移植を成功させた施設のため、肺移植に関する基礎研究(マウス、ラット、ブタ)を行っているラボが多い印象でした。
Marc de Perrotラボ

Marc de Perrotはスイス出身の現在51歳、呼吸器外科医で、トロント大学の教授です。一般呼吸器外科医として肺癌手術、肺移植を普段行っていますが、専門は悪性胸膜中皮腫、慢性血栓塞栓性肺高血圧症です。日本では手術療法の頻度が少ない慢性血栓塞栓性肺高血圧症ですが、欧米では手術療法の頻度は高く、症例は北米から集まり、週1または2例の手術が行われていました。悪性胸膜中皮腫も週1例の手術が行われていました。
Marc de Perrotラボのメンバーは、Marc de Perrot、スタッフ2名(共に中国人[医師])、ラボマネージャー1名(中国人)、ポストドク5名(日本人2名、台湾人1名(呼吸器外科医)、中国人1名(医師)、カナダ人1名(研究者)、1名の大学院生(カナダ人)、数名の学生(summer student[山口大学でいう自己開発コース]、医学部入学のための推薦状取得目的)で構成されていました。悪性胸膜中皮腫または慢性血栓塞栓性肺高血圧症に関する動物研究、臨床サンプル研究を行なっています。月曜日から金曜日までは朝8時30分から17時までがdutyでした。毎週水曜日にラボミーティングがあり、研究の進歩状況、実験プロトコールについてプレゼンテーションを行います。時間はたっぷりあるため、私の研究だけで毎週30分程度はディスカッションをしていました。
さらに週1回Latner Thoracic Surgery Laboratoriesのランチセミナーがあり、各ラボの研究者が持ち回りで研究内容を発表します。1年に1回担当が回って来ました。発表時間は45〜60分間もあり、聴講者は約80名程度と多く、発表途中でも質問がどんどん飛んでくるため、今まで経験がないくらいに緊張しました。またLatner Thoracic Surgery Laboratoriesでは肺移植に関する臨床研究を行なっており、3ヶ月に1回(1週間)は肺移植サンプル収集のon callが回ってきました。2日に1回は呼ばれ、1回呼ばれると肺移植開始から終了までサンプルを収集しないといけません。夕方から夜中に呼ばれることが多く、毎回ストレスな1週間でしたが、普段見ることのできない肺移植手術(clamshell開胸)を見学できたのはとても勉強になりました。
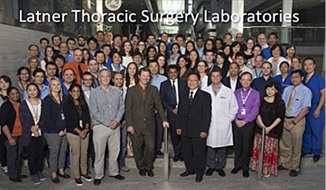

日本人ラボメンバー
私の所属するMarcde Perrot ラボには九州大学第 2 外科から呼吸器外科医が 1名、留学されていました。Toronto General Hospitalは肺移植が年間200例以上行われており、Latner Thoracic Surgery Laboratoriesには日本で肺移植を行なっている、または肺移植の準備をしている施設からの留学生(京都大学、東北大学、東京大学、大阪大学、岡山大学、九州大学、慶應大学、熊本大学、北海道大学など、常時15〜20名は在籍していました)が多かったです。
その多くは30〜35歳で、2年半から3年半で基礎研究の結果を出し、clinical fellow として 肺移植(senior fellow が術者)の研鑽を積んで帰国されていました。
また Toronto General Hospitalの胸部外科には日本人の安福和弘先生が教授の一人として在任されており、多くの日本人(呼吸器外科医、呼吸器内科医や医療技術者)が所属されていました。九州大学第2外科の先生をはじめ、多くの日本人ラボメンバーには、研究は勿論、生活に関しても大変お世話になりました。
研究内容について

Marc de Perrotは悪性胸膜中皮腫に対して術前放射線療法(強度変調放射線治療[IMRT])後に胸膜肺全摘出術を行い、良好な成績(2年生存率の改善、術後無再発期間の延長)を得ました。
私はこの術前放射線療法の免疫的効果について研究を行いました。術前放射線治療は当初は病勢コントロールと切除マージンの確保を目的としていたようでしたが、様々な研究報告からリンパ球をはじめとする免疫細胞を介した免疫賦活効果があることがわかってきました。
まず、私は悪性胸膜中皮腫のマウス皮下腫瘍モデルまたは胸膜播種モデルを用いて、放射線治療後の照射腫瘍への移入細胞をフローサイトメトリーで解析しました。照射後は抗腫瘍効果のあるCD8+T細胞が腫瘍内へ移入することがわかりました。
それに続いて免疫抑制性の制御性T細胞(Treg)が腫瘍内に多く移入し、CD8+T細胞の抗腫瘍効果を減弱させることがわかりました。そこでIL-15併用投与でCD8+T細胞を増殖、機能向上を促し、大量のCD8+T細胞の腫瘍内移入を促進させ、さらにDTA-1(抗GITR抗体)併用投与で、腫瘍内に移入するTregを選択的に消去させることに成功しました。これらIL-15/DTA-1併用投与により、放射線治療の免疫効果を増強させることを証明しました。
さらに悪性胸膜中皮腫の微小転移モデルを独自に作成し、微小転移病変に対するIL-15、DTA-1併用放射線治療におけるabscopal effect (非照射部位の抗腫瘍効果)の増強効果を証明しました。現在、論文作成中で、近日、投稿予定です。私の留学が急であったため、本当はresearch fellowの空きがなく、留学当初は私の研究課題はない状態でした。
しかし、臨床における現課題(悪性胸膜中皮腫に対する術前放射線治療後の手術療法は無再発生存期間の延長が改善するものの、術後局所再発や遠隔転移により再発率は高いまま、完治症例は増加していないこと)を解決できるような研究プロトコールを自ら計画し、仮説を証明することができました。まだ論文がアクセプトされていませんが、これらの成果を2年間で出せたことは自信になります。
現在、私が動物実験を行ったプロトコールを参考に術前放射線免疫療法後の手術療法に関する臨床研究が開始される予定のようです。
生活、休日の過ごし方

私の職場はトロントの中心部にありました。肺移植サンプルの on call があるため、職場から徒歩5分程度のコンドミニアムに住んでいました。トロントは移民が増えていて、空き賃貸物件は少なく、家賃が年々上昇している状態でした。私は妻と2人で渡加しましたが、家賃約20万円の1DKに住んでいました。学生並みの狭い部屋でしたが、80階建てコンドミニアムの27階に住んでいました。おそらく今後このような高層階に住むことはないと思います。
治安は日本並みとまでは言えませんが、一般人の銃所持が許可されていないこともあり、一般に「外国」として想像されるよりもかなり良く、世界で最も住みやすい都市として毎年の様に上位に位置づけられており、日本からの留学生にとっても非常に住みやすい環境です。夜中まで飲み歩いても危険な目には合いませんでしたし、そのような話は聞きませんでした。
休日は車を持っていななかったので、近くで過ごすことが多かったです。公園やトロント島へ遊びに行ったり、近所のイベントに参加したり、夏は家のベランダやパティオでお酒や食事を満喫しました。また日本人家族と共に自宅パーティーやキャンプを楽しみました。

トロントはMLBのToronto Blue Jays、NBA の Toronto Raptorsの本拠地です。ダルビッシュ有投手、田中将大投手や大谷翔平選手のプレーも観戦することができました。さらにNBAは観戦チケットが高かったですが、スーパープレーに熱狂し、研究の辛さを一瞬忘れさせてくれました。2018-19年シーズンはToronto Raptorsがchampionとなり、NBAの優勝パレードを間近で見ることができました。これはNBAファンには自慢できます。
また海外留学の醍醐味といえば、週末やholiday seasonの旅行です。カナダには、ナイアガラの滝やオーロラが見えるイエローナイフ、世界遺産のカナディアンロッキーなど、観光スポットがたくさんあり、さらにはニューヨークやフロリダ、キューバ、メキシコなど一生に一度は行きたい観光地もトロントから数時間で行くことが可能です。
私もオタワ、モントリオール、バンフ(カルガリー、カナディアンロッキー)、ニューヨーク、フロリダ(ディズニーワールド、ユニバーサルスタジオ、ケネディー宇宙センター)やメキシコ(カンクン)に旅行に出かけ、いい思い出を作ることができました。
おわりに
最後になりましたが、本留学に際して留学を快くお許しいただき、かつ多大なるサポートをしていただいた濱野教授、上田先生と田中先生をはじめ、第1外科医局員の皆様に心よりお礼を申し上げます。