明日香健輔さん連続インタビュー(第二弾):阿東に根を張って生きる
お待たせしました。明日香 健輔さんの連続インタビュー第2弾です。
このインタビューの趣旨・明日香さんのご経歴に関しましてはインタビュー第1弾をご覧下さい。
(第二弾)阿東に根を張って生きる
–––––:そうなると、山口では、どんなことを今日に至るまでやってこられたのでしょうか。
明日香さん(以下 明):山口にいながらも、東京に行ったりしていましたし、いろんな仲間のつてを介して仕事をしてきました。これなんかはパイオニアの自転車のナビゲーションです。これを企画として持ち込んで、パイオニアさんと一緒にやらせてもらったりしました。

自転車のナビゲーション
住んでいる阿東では、移動販売車による地域内巡回と見守り活動をしているNPO法人ほほえみの郷トイトイさんともコンシェルジュサービスを一緒に作ったりしてきました。移動販売車で地域を周った時に、いろいろ御用聞きで話を聞いたりするのをデータベース化しようというものです。あと、これは一人暮らしのお年寄りがどんどん増え始めているので、都会に住んでいる娘さんや息子さん、お孫さんなどに、(サザエさんの「三河屋でーす」ではないですけど)移動販売で行った時に「こんにちは」と挨拶する最初の十数秒を、帽子のツバにつけた小型カメラで自動的に撮らせていただいて、その様子を都会のご家族に配信して安心してもらうというものです。ビデオを構えると皆さん「いやいや」となったりするので、最初の10秒だけ、元気ですよって。
もうひとつは、阿東内での売上人口もどんどん減っていくことになるので、トイトイさんとしてもどうやって売上を増やすかというところで、そういう都会に住む方々に、このコンシェルジュサービス(安心サービス)をきっかけに、ちょっと送料が高くつくけれども自分の親のいる地域のスーパー(トイトイさん)からものを買ってもらおうということで。ふるさと納税ではないですけれども、そういうサービスを使って、地域内ではなく、地域外のユーザーを増やすということを、一緒に実証的に模索してきました。これをご縁に、いろんなことトイトイさんと今も並行してやっていますね。
あと、私の会社の今の主要な稼ぎ口は、実は手術器具の管理システムなんです。手術器材にRFIDというタグをつけて管理するというシステムを構築しました。大きな病院では、メスやナイフ等の手術に使う鋼製小物が2万~3万点あると言われています。ところが、そのどれが古くなったのかがわからなくなったり、手術器材はとても高価なのですが、なくなったことすらもわからないということもあって、結構管理がむずかしいんですね。

手術器具管理システム
–––––:術後に器材がなくなってしまっていたら大問題ですよね。
明):そうです。いま病院は何で一番稼ぐかというとやっぱり手術なんだそうです。大学病院でも手術室がいくつかあったら、それをいかに効率よく回すか、いかに手術の回数を効率よくこなすかが大事で、手術器材の紛失なんかでそれが止まったら大打撃なわけですよ。
この後、術後の器材がエレベーターに乗っていって洗浄されて、また今度はコンテナボックスにいろんな手術別に詰められるんですね。これを「組み立て」と言うんですけども、洗浄されて組み立てされて、また保管されて。それで手術の前日にいるものだけを取り揃えて手術室へというルーティーンがあるんですよ。このルーティーンもちゃんとどの手術でどれが使われてとか、ちゃんと洗浄して組み立てた後に滅菌できているかとかが問題になります。滅菌という行程も非常に大切で、滅菌もガスやプラズマなど、器材によって違うらしいのですが、いろいろな方法があります。それも本当に滅菌されたのか、あとで事故が起きたときに、きちんと間違いなくやりましたということ等を紙ベースや経験則ベースではなく、ちゃんとシステム化していきましょうというのが今医療現場でもトレンドなんですね。
–––––:なるほど。しかし、こんなに小さいもので、本当に多くの情報を管理しているのですね。
明):そうなんですよ。特に組み立てるところでは、先生によって使う器材が違ったり、病院の中でもそういう組み立て方が決まっていたりするんですけどね。今までは、朝から晩まで時間をかけて手術のためにそれ専用の人たちが準備していたわけなんですけども、それが今では全部の器材にRFIDタグがあるので、アンテナに通して「ピッ」となってOKという。それで、間違いなくそこを通しましたというログ(手術前後や滅菌前後など)が全部残るんですよ。
–––––:わかりやすい一つのDXのかたちという感じですね。
明):そうです、リスク回避的なDXですね。医療裁判なんか、一発やったら何億円ですからね。そんなことよりシステムを構築したほうが安いという話なんですけど。
–––––:今はこれが明日香さんの一番大きなお仕事ですか。
明):そうです、今はずっとここ10年ほどは。実は、この仕事は名古屋にもともとある医療系の医療ガス(医療酸素、窒素、水素などを扱う)の会社からのものなんです。東海地方で約7割の医療ガスのシェアをもっています。それでガスも昔ほど高くは売れなくなって、他のこともしていかないといけないというときに、たまたまそこに僕が出会った知り合いの方が勤めていて、「ソフトの相談にのってくれない?」と言われて話を受けることになって、かれこれ10年これを一緒にやらせてもらっています。
–––––:そういうことやっている傍らで、明日香さんはその他にもいろんなお仕事を?
明):はい、そうですね。「副業」なんですけども、フィンランドの薪ストーブを売ったりもしていて。大陸で25億年くらいかけて圧縮された「ソープストーン」という、すごい重い石なんですけども、これ組み上げたものです。3代、4代にわたる一生ものとして使える薪ストーブなんですけども。北欧は寒いので、冬の間ずっと暖炉に薪が入っている状況なんですって。
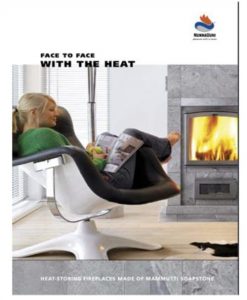 |
 |
輸入薪ストーブ
–––––:これはご自宅でも使われているんですか?
明):そうです。総代理店は神戸にあるんですが、私自身もこのストーブが気に入って、すごいいいストーブだからと言っていたら、「明日香さん、代理店しない?」という話になって。滅多に売れるものではないんですが、ストーブで仲良くなって、いろんなお付き合いさせてもらっている人も結構います。みんな、すごくいい人が多いです。
明):この写真に写っているのは私と息子なんですけども、阿東に来てからは、地元の営農法人さん(株式会社十種の郷さん)で田植えのお仕事も手伝いさせてもらっています。基本的に、このかたとは現金でのやりとりはしていません。最初から「手伝った分だけお米ください」という関係です。

田植えを手伝う明日香さんと息子さん
明):だから、阿東に引っ越してきて、ちょうど例の会社が倒産じゃないですか。リーマンショックの先駆けとも言われていまして、それから2年間は本当にシステムの仕事は東京に行っても名古屋に行ってもなくって。もうみんな「明日香さん、何か仕事ない?」って尋ねてこられるんだけど、「いや、こっちが仕事を探しにきてるんだけど」という状況でした。
–––––:山口行き前後が、ちょうどそういうときだったんですね。
明):そうです。だから、今から思うと、非常にいい時に移住しています。だって、街中に住んでいて倒産して仕事がなくなったら、家内なんかから真っ先に「明日からどうすんの?家賃どうすんの?」と言われるような、たぶんそんな話ですよ。でもここ(旧阿東町徳佐)にきていましたから、家賃は心配いらないじゃないですか。食べ物もこういうふうに営農法人で手伝いしていたので、野菜はもらえるし、お米の心配もいらないしで、家内から責められたことは一度もなかったですね。むしろ、その仕事がなかった2年間で、本当に一番田舎らしいことをすることができました。
–––––:本当にタイミングがすごくよかったというか。
明):すごくよかったです。
–––––:ご縁ですね。
明):そうですね、ご縁ですね。こことは、いまだにお付き合いさせてもらっています。
–––––:すごいですね。システムの開発しながら、地元の方も含めて本当にいろんな方と関わりながらで。
明):そうです。これは先ほどお話しした方のところの写真で、写っているのは、息子です。田植えはやったことがありますか。
–––––:はい、あります。
明):田植え機での田植えは?
–––––:いや、見るだけですね。手で植えるくらいのことしかやったことないです。
明):はい、はい、それで十分です。これ育苗のハウスなんですよ、田植え機に乗せる前の。真ん中は、これ1枚ずつがパレットになっているんですよね。
–––––:それを田植え機に乗せてぐるぐるまわして植えていくんですよね。
明):そうそう。苗が10センチくらいに育つまで、このハウスの中で育てているんですけど。田んぼって1枚2枚じゃないですし、このかたなんて3反から4反の田んぼが何十枚も、40枚50枚もあるんですよね。この種類の苗はどの田んぼに植えるからいつ植えるぞとかというのを計画的に。約2週間から3週間にわたって田植え期が続くんですけど、苗も計画的に育てないと、要は田植えするときに一番ベストな状態にならないといけないので、温度管理が大事になっています。このハウスでは、プール育苗といって、水を流したりして温度を管理しているんですが、それでも何度か40度を超えることもあって、そのときにどこか遠くに行って帰ってきたらもうアウト、もうそのハウスは全棟アウトということもありました。
この営農法人には今ハウス5棟あるんですけど、一棟がパーになりました。結構なダメージで、パーにして挙句の果てに苗をまた今度農協から高い苗を買いなおさないといけないという話になるので、「なんか僕がやりましょうか。温度管理くらいだったらできますよ」と言って話したら、「とにかく温度が40度を超えたら、なんか知らせてくれたらそれでいいわ」って言うから、「じゃあパトライトでいいですか」って。これがパトライトです。

ビニールハウスに設置したパトライト
–––––:一定の室温を超えたら光るとかですか。
明):そうです。40度を超えたらこれがくりくりくりくり回るんです。それで、どこかに行っていたらいけないので、じゃあ一応LINEにも情報をとばしてあげましょうねということで、「今温度40度超えたよ」というメッセージをとばして。
–––––:そういうことができるんですね。
明):そうです。ただそれだけ。それだけなんですけども、もう今年で3年目ですが、これを設置してから育苗がパーになるという事故はなくなりました。
–––––:あー、そうですか。
明):なくなりました、はい。
–––––:息子さんと一緒にこれを?
明):そうです。
–––––:すごいですね。
明):なんてことはないんですけどね。でもお金をかけずにこんなのほんとにラズパイを使って、この太陽光パネルも去年からつけたんですけど、なんか線引っ張ってくるのは大変だからということで、近くの自動車屋さんに行って、「廃棄になる蓄電池を1本ずつください」といってもらってきて。で5ボルドくらいなので、もう知れていますし、充電はこれで十分できますので、全部で1万円くらいのものですけどね。これを今、3台くらい設置してあげました。
–––––:ちょっと話がそれるかもしれませんが、息子さんはどうしてこういうことに関心をもたれて今一緒に働くことになったんですか。
明):息子はもともと高専に行っていて、ロボット機械とかをやっていたんですよ。でも途中で嫌になったと言って、ちょうどコロナ禍になる前に辞めてしまいましてね。で、「就職するわ」とか「プログラム開発が面白そうだからそっち行くわ」とか言っていて、「そうか~」と言っていたんですよ。そう言っていたらコロナ禍になって、いやちょっと今、大阪や東京に行くのはどうなんという話になりましてね。「まあ、あんたちょっとうちの仕事手が足らんから手伝ってくれるか~?」って。ちょうど息子だけでなく、もう一人同じくらいの年の子が一人いたので、息子一人だけだとどうしようかなと思っていたんですけど、その子がいるならまあ二人ワンセットで。息子はそのうち出ていってもらってその子が残ってくれたらって。でも、結局息子一人が残ってるんですけどね(笑)。
–––––:じゃあ明日香さんの近くでいろいろ教わって一緒にやっているという感じですか?
明):そうです。今はもう教えること何もないですけど。実際、先ほどの地元の農場でも田植え機にのって幼い頃から田植えを手伝っていましたから、そのかたが今年は一棟全滅で困っているらしいでと言うと、「ええー!?」とかって。温度管理するだけでええらしいんだけど、ほんなら一緒に作ろうかという話になりました。
–––––:幼い時からここで育って、今、お仕事で地域に貢献されているという。
明):そうです。だから「一棟パー」だと言われて、「ええー!?」とわかるんですよね、大変さが。
–––––:今度また別の機会に、息子さんにもいろいろお話をぜひお聞きしたいですね。
明):そうですか、ぜひぜひ。また機会があれば。この長男もそうですけど、今、大学生の次男と、それからこの地域の子ではないんですけど、なんかどうもシステムのことに興味がある子がいるみたいで、「明日香さん、話だけでも聞いてもらえませんか」とそのお母さんからお話しがあって、「いいですよ」と言ってお会いしました。それで、こんなシステムを作りたいんですという話になったから、年も近いお兄ちゃん(うちの息子)たちもいるから、そのお兄ちゃんと話ししてもらいながら、よかったら一緒にやろうかって。今こっちへ来ているんですけど。その3人が、今阿東地域の困りごとのシステム開発とかも、やってくれ始めています。ちょうどね、3日前くらいに、中国新聞の方がその子たちのことを記事*[1]にしてくれました。
–––––:これはとても興味深いですね。
明):去年から地元の阿東中学校で校長先生にご協力いただいて、1学期に6時間ほどIOTの授業をさせてもらえるようになりまして。この授業だけじゃなくて、他にもいろいろあるんですよ、マーケティングの授業とか。他の地域おこしをしている方々も授業をやったりしているんですけども、その中のIOTのところだけ、うちの若い子たちにちょっと授業をさせてあげてくださいということで。で、マイクロビットをちょっと使って授業をしたんですけども、これをやっぱり続けましょうよということで、夏休みとか部活の時間をちょっと削って割いてもらって地域学習というかたちで。今日も90分、午前中に行ってきたところなんです。やっぱり地域の子どもが地域の問題とか課題の一番近くにいるわけだから、それをなんとかしてもらえるように、僕たちはそのインフラとか土壌とかを今つくっていってあげないといけないんじゃないかということで。まあ将来、この中学生の中から何人か仲間が出てくるかもわかんないぜってそんな話もしています。
だから、単に今、小中学生もプログラミングが必須化されて、現場の先生方もおそらく大変だろうなと思っています。私も山口の教育委員会に呼ばれて、ちょっと意見聞かせてくれということがあったんですけど、「いや、子どもたちの前に、親御さんを教育したほうがいいですよ」といって。もうたぶん親がパニックですよ、はっきり言って。プログラムの学習塾に子どもを入れないといけないんじゃないかとか、うちの中学校のプログラミング教育はどうなっているんだとか言ってね。親御さんを交えて子どもたちとプログラムってこんなことをやるんだねとか、こういうことはできるけど、こういうことはできないんだねとかいうのを理解してもらう。そうやって先生方のプログラミングスキルも上げていってもらわないと、いきなりプログラムを教えろと言ったって無理ですよ、はっきり言って。
山口市から私にも委託があったので、ルビー言語やプログラミングスクラッチを使って、レゴで作ったちょっとした自動車を動かすということを子どもたちとやってみました。30人~40人の中でもともと1人2人、そういうことに興味があって面白いという子がいたりするんですけども、でも、じゃあこれからプログラムを自分でやってみるかというところにはなかなか結び付かない。ちょっとした困りごと、地域の困りごとにプログラミングを使うとこういうことできるよという着地点ありきで話をしないと。なかなかプログラム学べと言ったって、はっきり言って拷問ですよ。アルゴリズムだけを学んで楽しい人がいるんですかね。
–––––:今度、機会があったら、中学校での活動もよろしければ見せていただきたいです。
明):ぜひぜひ。ほんとに小さなマイクロビットを使って、シューティングゲームを作ろうかとかって言っていますよ。インベーダーゲームの簡単なやつですけどね。
–––––:はい、僕自身がほんとに素人なので、お話を聞いているだけでもすごく面白そうです。それも、中学生より少し年上の若いかたたちが教えているとのこと、ぜひ見せていただけると嬉しいなと思います。
- 次回、第三弾では、山口市阿東を拠点に様々な「複業」に取り組む明日香さんですが、そこに一貫する「チューニングしながら生きるということ」についてお伝えします。
- ※ *[1] 中国新聞「若者3人、身近な課題や中学生の指導にデジタル活用 山口市阿東」2023年7月31日、https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/340068 (最終閲覧:2023年11月16日).「※全文閲覧には会員登録が必要です。」
- 明日香さんインタビュー第一弾はこちらから
- 明日香さんインタビュー第三弾(最終回)はこちらから

